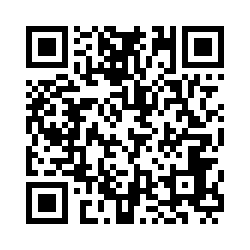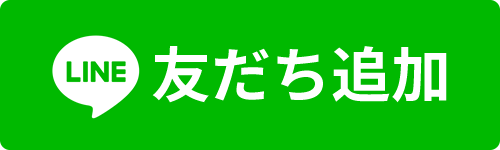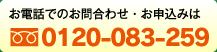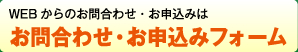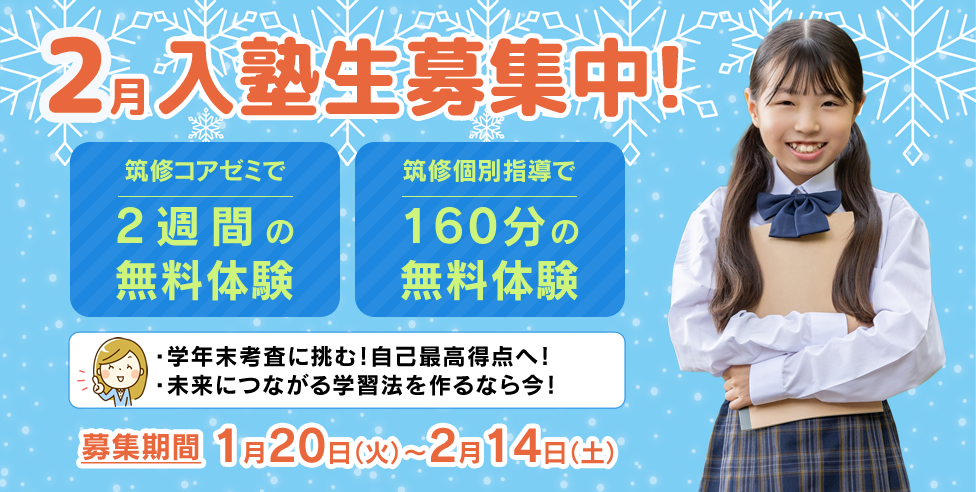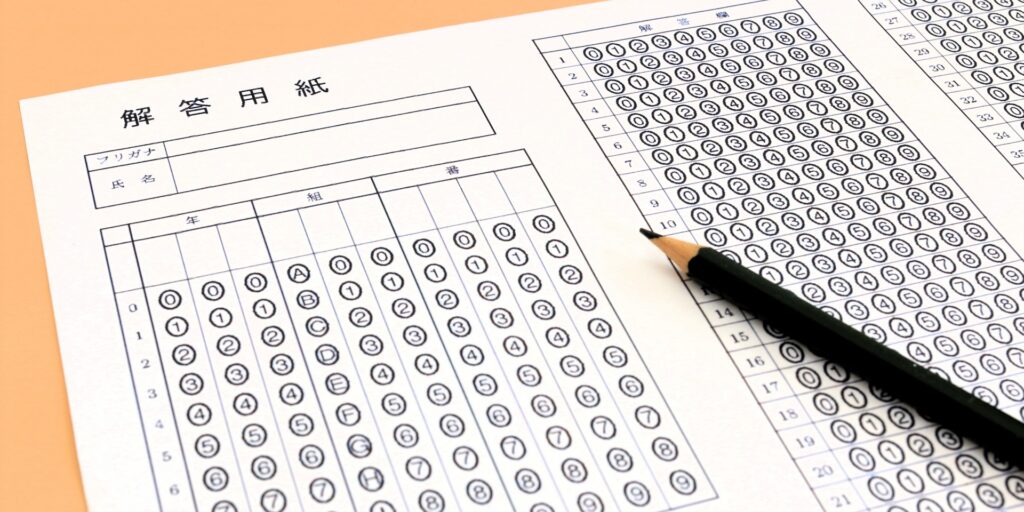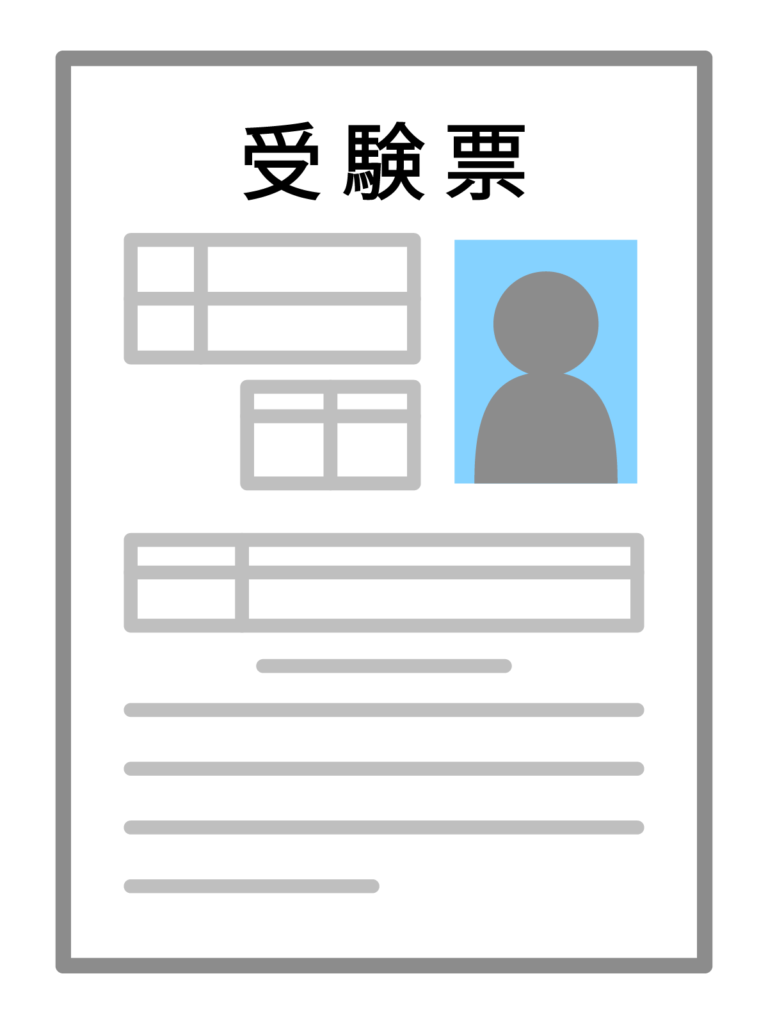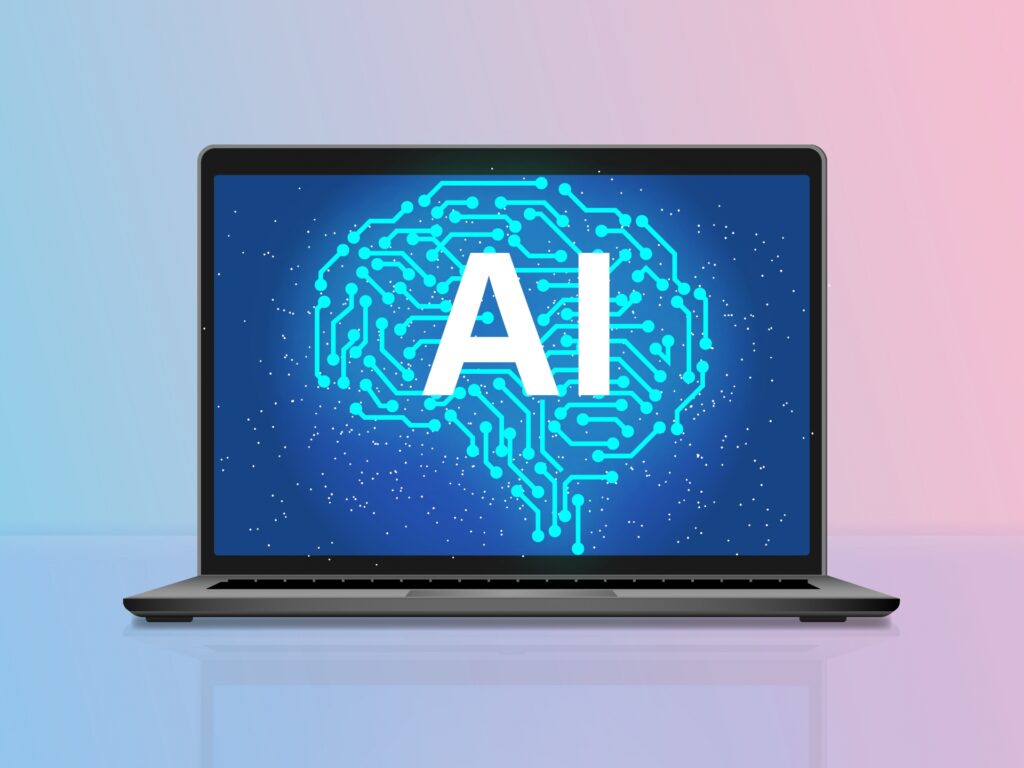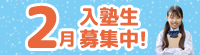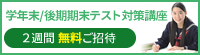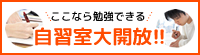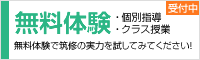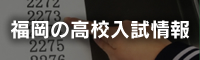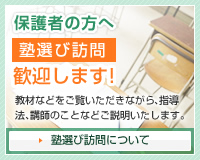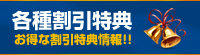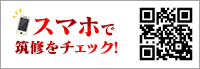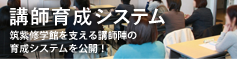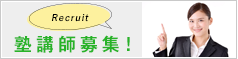夏休みや秋口になると、「そろそろ過去問に挑戦しようかな」と考え始める受験生も増えてきます。
しかし、過去問演習は“ただ解くだけ”では効果が出にくく、
むしろ「やったのに成績が伸びない…」という状態に陥ることもあります。
今回は、過去問に入る前に必ずやっておくべき3つの準備についてご紹介します。
正しく準備し、正しく活用すれば、過去問は最高の実戦教材になるのです。
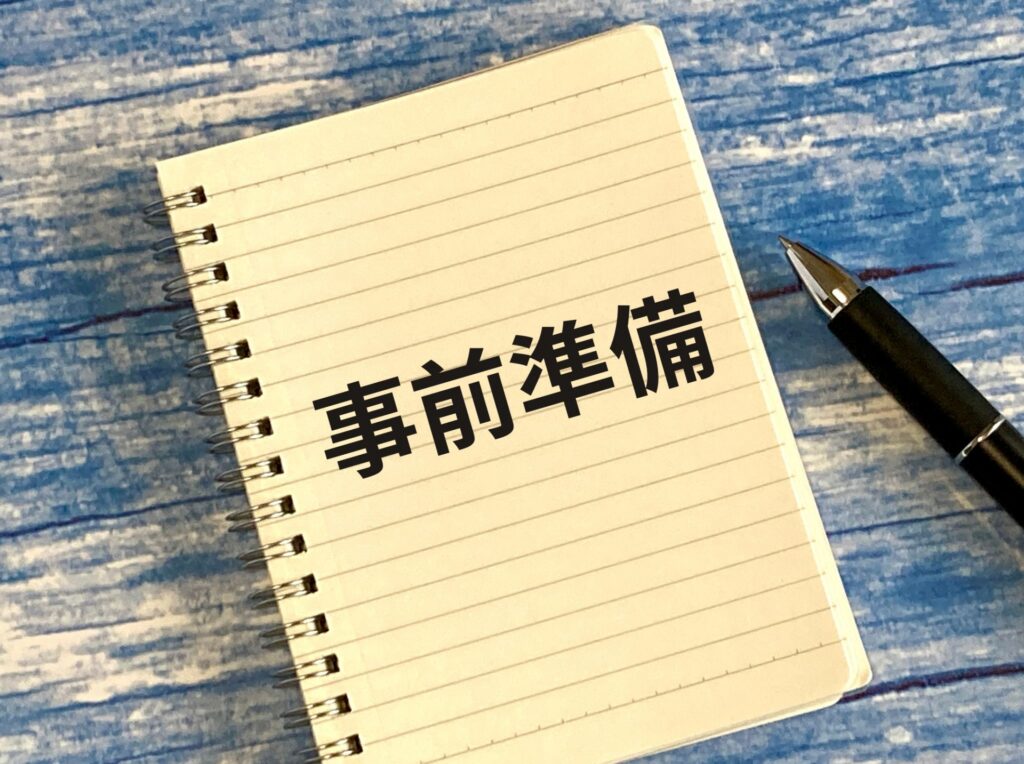
基礎事項の総点検~知識の抜け漏れは命取り~
過去問は、応用力・実戦力を問うための問題です。
言い換えれば、
土台となる基礎力が固まっていないと、まったく歯が立たない
ことも珍しくありません。
- ・英語:文法の基本(時制・不定詞・関係詞・仮定法など)を正しく理解しているか?
- ・数学:教科書レベルの公式や典型問題がスラスラと解けるか?
- ・国語:語彙や文法の知識に穴はないか?
もしも「なんとなく分かってるつもり」レベルの知識で過去問に入ってしまうと、
「何がわからなかったのかさえわからない」という危険な状態になります。
まずは、これまで学んだ内容を単元ごとに確認し、“自信のない単元”を洗い出すことが先決です。
志望校の出題傾向・配点の把握~目的なき演習は効果半減~
過去問演習は、“その大学で点を取る”ための演習です。
だからこそ、
「その大学がどんな問題を出題するか」
「どの科目の配点が高いか」
を知ったうえで解く必要があります。
チェックすべきポイントは
- 出題形式(記述式かマーク式か)
- 問題量と制限時間のバランス
- 出題されやすいテーマ・単元
- 教科ごとの配点比率(英語>数学 など)
といった内容です。
たとえば、英作文が毎年出る大学であれば、文法の精度だけでなく
英作文の型やおおよその採点基準を理解しておくべきです。
「どの力が求められているか」を知らずに過去問を解くのは、
目的地を知らずに走るマラソンのようなものです。
演習と復習のルールを決めておく~解きっぱなしにしない~
せっかく過去問に取り組んでも、
「時間を測らずにだらだら解いた」
「答え合わせだけして満足」
では意味がありません。
過去問演習は“復習と分析”にこそ価値があります。
そのために、次のようなルールをあらかじめ決めておきましょう。
- 時間をしっかり測る(試験本番を想定)
- 解いた直後に答え合わせを行う
- 「正誤」だけでなく「なぜ間違えたか」を書き出す
- 解説を読んでも理解できない問題は、類題で補強する
さらに、「解けなかった原因」を分類するのもおすすめです。
- 知識不足
- ケアレスミス
- 時間配分のミス
- 問題文の読み違い など
このような“振り返りの質”が、次に解くときのスコアに直結します。
まとめ:過去問は“準備してから”が効果的!
過去問演習は、受験対策の中でも非常に重要なフェーズです。
しかし、その効果を最大限に引き出すには、準備段階での戦略が不可欠です!
【現在、以下のコースの申し込みを受け付け中です。】

夏期講習についての詳しい情報はこちらをクリック!
【小中高校生】自習室無料開放
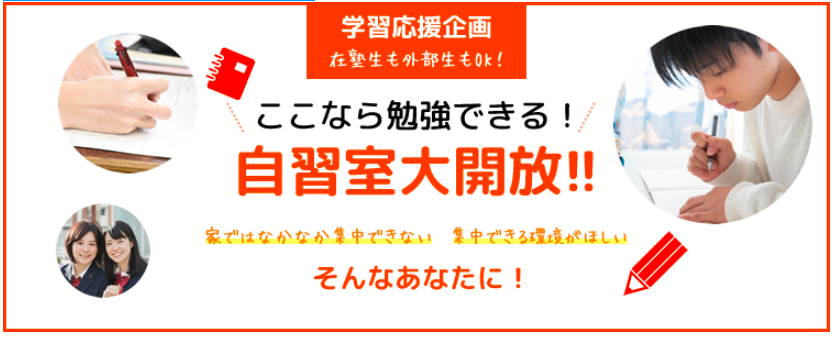
校舎開館中は自習室を使い放題です!
一部時間帯は講師にわからない問題の質問対応も可能です!!
★各コースお申し込みは…
①お電話…0942-75-7000(小郡大保校直通)
②校舎LINE…以下QRコードから「○○参加希望」とメッセージをお送りください。
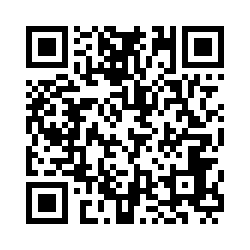
③ホームページお問合せフォーム
https://www.ganbari.com/pamphlet/
このブログはこんな人が書いています!
森 駿介
筑紫丘高校→九州大学理学部数学科卒業
塾講師歴11年 筑紫修学館歴12年